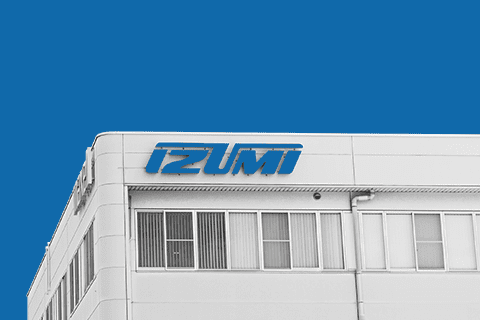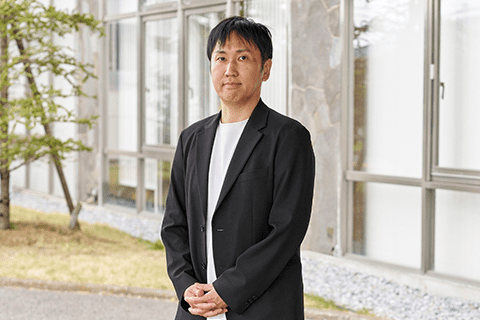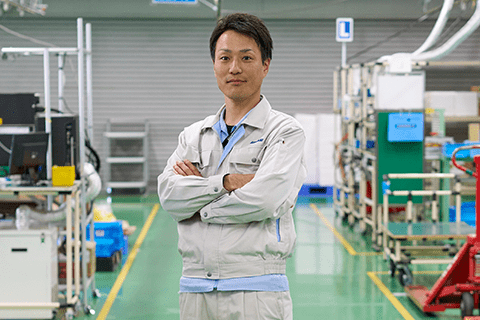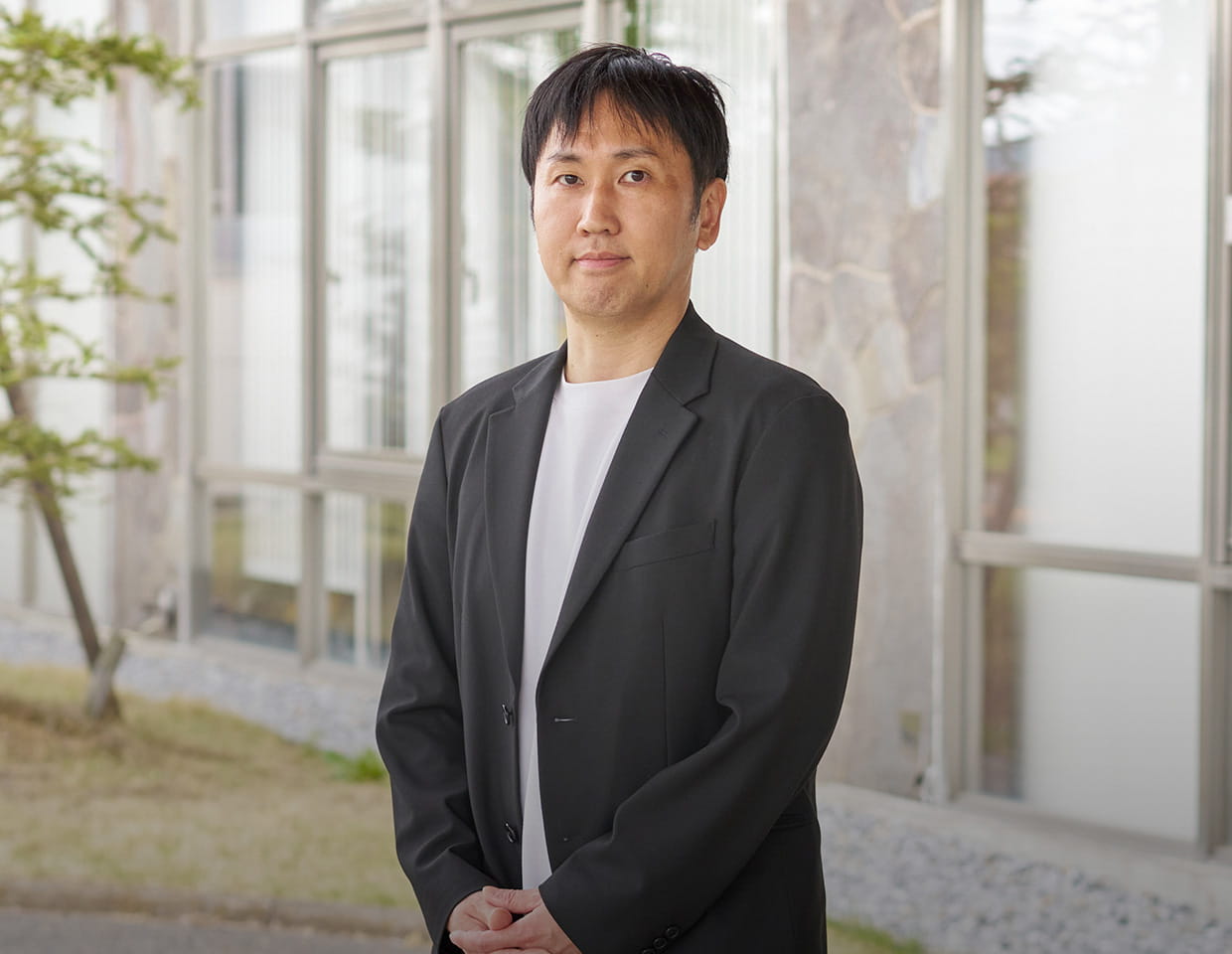「できない」と言わない姿勢が
実現させたプロジェクト
曽田 昂良家電技術部 設計課

Introducton
2020年新卒入社。今回のプロジェクトメンバーでは最年少。学生時代に学んだCADの技術を評価され、設計部に配属された。OEM製品や自社向け毛玉取り器のマイナーチェンジモデルの開発に携わる。企画、中国工場、製造、品質保証といった複数にわたる関係部署との調整に奔走。
製品開発のカギとなったのはどんなことですか?
粘り強く検討するマインドが生きた
設計を担当する技術部は、新たな商品の相談を持ちかけられたら「できない」とは言いません。部内で「できないと言ってはいけない」と指示されているわけではありません。ただ、上司や先輩はどんな相談にも「厳しい」などとは言わず、少なくともいったん持ち帰って粘り強く実現性を探ります。私もその姿勢を真似しています。この技術部のマインドが今回のプロジェクトでも生きたと感じています。
「Lint Remover Magewappa」のボディは手になじむ小ささを目指しました。木製では既存の毛玉取り器のような複雑な形状は難しい。木を成形するには円柱形が現実的だとすると、やはり現在のサイズくらいでないと手になじまないんです。機構としては大きなもののほうが設計はしやすいので、当然ハードルは上がったんですけど、トライアンドエラーを重ねて製品化にこぎつけることができました。
サポート役として一から開発する経験はありましたが、メイン担当としては初めてだったので、とても達成感の大きな仕事になりました。

「Lint Remover Magewappa」を生み出すために苦労したことは?
どんなときも使い勝手を大切にしたい
今回のプロジェクトでは、操作性と機能性を守ることを重視しました。毛玉を取るものなので、きちんと取れることは最低限の条件です。しかし、「Lint Remover Magewappa」はこれまでの機構とはまったく違います。既存の商品は取れた毛玉が横に吸い込まれていきますが、今回の新商品は垂直に吸い込まれていくんです。そこで、吸い込まれた毛玉が逆流して落ちていかないよう、刃の回転方向に工夫をしました。ここは非常に苦戦しましたね。
家電部門ではこれまでにない、少数生産というケースでもありました。コストの観点から、新たな部品点数を増やさないことに注力しました。刃などは既存の製品の部品を流用しています。
今回に限らず、いつも「使い勝手」を重視して設計しています。ユーザーの使う姿を想像するのは、やっぱりやりがいになりますからね。今後もこのプロジェクトに携わることができるのであれば、たとえば調理家電やドライヤーのように、多くの人にとって身近な家電の開発に携わっていきたいと思っています。

どんなところが今後に生きると思いますか?
木でできるなら何だってできる
一から新製品を作るというだけでなく、初めてのことづくしだったこともあって、いつも以上に他部署とのやりとりの多いプロジェクトでした。
小さなボディに安全装置を入れたことにも苦労しました。これは、外刃を外すと内刃が回転しなくなるという機能。内刃は鋭利なため、どうしても危険がともなうんです。当初、小さなサイズに安全装置を入れるのは難しいと考えて、設計からは外していました。しかし、品質保証部門から「メーカーとしての義務」という話があり、組み込むことにしました。
サイズを変えずに機能を増やすということにはだいぶ苦労がありましたが、結果、胸を張れる製品ができたので、品質保証を担当した香山さんには感謝したいですね。そうやって言いたいことを言い合える空気は、働きやすさという意味でも大きいと思います。
そして何より、「木」で新製品を開発できたことで、「何だってできる」という自信がつきました。布や陶器のほうが個体差や環境変化はまだ小さいですから。今後、金属とプラスチック以外の素材でも柔軟に対応できると思います。

Project Member
INTERVIEW
受け取ったバトン、つないだバトン
企画から、設計、品質保証、製造まで、プロジェクトに携わったメンバーが、どのようにバトンを受け取り、次へ渡したのか。
Lint Remover Magewappaの開発秘話をお届けします。
PRODUCTS
of GOES ON
長年受け継がれてきた技を未来へつなぐために。
地域の伝統工芸品のつくり手とIZUMIがとも
に開発したコラボレーションProductsです。